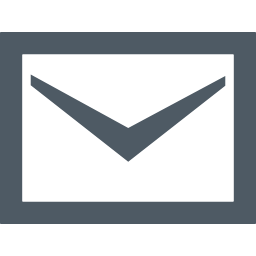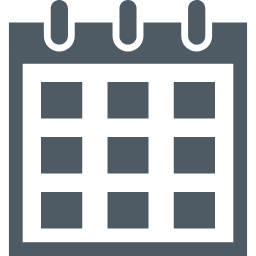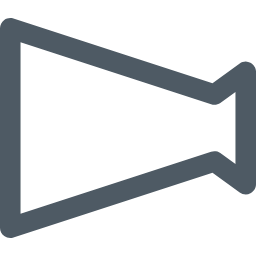近年、徐々に盛り上がりを見せている「eスポーツ」のなかでも格闘ゲームにおいて、上位ランカーのほとんどは日本人だということをご存知だろうか。この栄誉ある下地を作ったのがゲームセンター(以下/ゲーセン)だ。近年、大型店や老舗の閉店ニュースが相次ぐなど、暗いニュースが多いなか、“格闘ゲームの聖地”と呼ばれる老舗ゲーセンも苦境に立たされながらも、その灯を守り続けている。『ゲームニュートン』のオーナーであり、ユニバーサルグラビティー代表の松田泰明氏に、ゲームセンター文化の現在と未来について話を聞いた。
【写真】ゲームの“見本市”『東京ゲームショウ』にコンパニオン&コスプレ美女大集合
■日本初のゲーム大会実況を開催 “格闘ゲームの聖地”からウメハラ、ときどなどレジェンドを輩出
そもそも、なぜ板橋区・大山に“格闘ゲームの聖地”が誕生したのか?さまざまなメディアでも語られている通り、松田氏は、高校卒業後に志村三丁目にある『ゲームニュートン』のオープニングスタッフとして就職。90年代のゲーセン人気に乗った時期もあったが、その後下火になる業界に、親会社は撤退を決定。そこで松田氏は「退職金代わり」に店舗を譲り受け、オーナーになることに。
「ここを舞台に、ゲーム大会の模様を撮影し、そのファイルをインターネット上にアップロードしたほか、Ustreamやスティッカムなどの配信ソフトが登場してからは大会の実況も配信。ニコニコ動画よりも前の話であり、おそらく日本のゲームセンターで初めてゲーム実況をしたのはうちではないか、と言われています」
その後、さまざまな施策を取るなかで、格闘ゲームの大会を主催すると、これが大ヒット。『ゲームニュートン』志村店の大会が都内を中心に有名になり始め、ついには2~300人参加と店内で収まらない規模に…。そこで大山にも店舗を設け、2店舗で営業を始めた。
この大会主催のノウハウを生かし、松田氏はゲーム界での“世界最強決定戦”ともいわれる『闘劇』(2012年に仮閉幕)の創設メンバーの1人に。当時はゲーム雑誌が大会を行っていたが、参加が抽選式。どんなに強くても抽選に漏れれば参加ができない。『闘劇』はこれを改革し、日本全国の各地方で予選を行い、その勝者たちが本戦に挑む「甲子園」型を作った。誰もが平等に腕を競いあい、“本当の”日本一を決める大会を作ったのだ。この『闘劇』からは、今の「eスポーツ」の格闘ゲームジャンルで大活躍しているウメハラ氏、ときど氏、ももち氏らそうそうたる世界のトップ選手を輩出。“格ゲー大国日本”の原点となった。
「この大会に出るために、多くのプレイヤーが毎日のように通って練習していく。そこで利益は生まれましたし、盛り上がりも作れた。彼らを見て感じるのは皆がアスリートだということ。ゲーム自体は2~3分で終わる。でも、その2~3分のために、結果を出すために、彼らは1年練習をし続ける。練習すればするほど自分の分身は強くなる。彼らの血のにじむような努力、勝敗でのそれぞれの涙。すごくドラマティックですし、彼らの格好良さを世界に伝えたかった」
■「正直、ゲーセン単体では赤字」家庭用ゲーム、スマホ以外にもある“ゲーセン文化”衰退の理由
こうして現在の「eスポーツ」に続く流れを作る一方、90年代後半以降、ゲーセンは次々と姿を消していた。最盛期には30,000店近くあったといわれる店舗は、現在2,500店ほど(専業店)とも言われている。この急激な衰退の理由はさまざまな理由が考えられるが、その大きな理由は、やはり家庭用ゲーム機の台頭。
「『ファミリーコンピュータ』など家庭用ゲーム機黎明期は、ゲーセンの筐体のゲームが移植されても、スペックや仕様において、筐体の方が優れている時代が続いていました。これに陰りが見え始めたのが『プレステーション2』が出た頃(2000年)。画質や操作性が一気に上がってきた。さらにその後、スマートフォン登場以降は、無料でできるスマホゲーム(アプリ)にも客を奪われました」
実はこれ以外にも衰退の理由があると言われている。筆者が独自に調査したところ、2001年頃から、ゲームメーカーが「従量課金制」を導入し始めた。それまで、ゲーセンは初期投資として、ゲーム筐体並びにゲームの基板を購入。その投資さえ終えてしまえば、ゲームに支払われるコインはすべてゲーセンの利益になった。だが「従量課金制」では、オンライアップデート、新キャラ、新アイテム登場、オンライン対戦の費用、サーバー維持費といった名目で、ゲームが行われた回数分、その対価をメーカー側に支払わなければならない。4から6割弱をメーカー側に支払うことで、利益が激減。家賃、店舗管理費、人件費などが重くのしかかり、耐えられないゲーセンは閉店に追い込まれていった。
“格闘ゲームの聖地”として、都内のみならず、その名を世界にもとどろかす『ゲームニュートン』も、その経営は決して楽ではないという。
「正直な話をすると、今『ゲームニュートン』の2店舗それぞれ、単体では赤字です。私個人が、ゲーム関連のさまざまな仕事をいただいているのでそれで補填したり、コロナ禍で営業ができなかった時期は、常連さんやこのお店のことを知ってくれた世界中の人たちが、寄付してくれてなんとか保っています。中小のゲーセンは、持ち物件で家賃がいらないとか、よほどの特別な事情があるところ以外は残れないと思う。昨今、ゲーセン閉店のニュースが続々と流れていますが、このご時世、大型店以外で生き残れない、今後増えていくことはない、というのがゲーセンの真実だと思います」
■「今の子どもはゲーセンに『いかないこと』が当たり前」だが、オンラインでは味わえない空気感がゲーセンの魅力
かつて、ゲーセンが全盛期だったころ、大人やPTAからは「行ってはいけない」と忌諱される存在であり、当時の子どもたちは、「行きたいけど行くのは悪いこと」という複雑な想いを抱きながらも、憧れる場所だった。そこには学区も学年も超越し、不良もオタクも、ゲーム好きも同居する日常生活とは異なる社会が存在。大人になっていくためのある種の“通過儀礼”を経て、子どもたちは自分自身の世界を広げ、“学校では教えてくれないこと”を学んでいった。だが月日は流れ、今、子どもたちの姿はほぼない。
「今の子どもたちはゲーセンに『いかないこと』が当たり前になっている。ここ10年くらい、小中学生同士で来店なんてほとんど見たことないです。これだけ娯楽がいろいろあって、スマホで無料のゲームができるようになって、わざわざお金かけてゲーセンって、そこまでの魅力がなくなってしまったのかもしれませんね。高齢化は否めません(笑)。80年代、90年代のゲーセン文化から変わってきています」
業界歴が長い分だけ、ゲーセンの廃れゆく運命をより間近で感じている松田氏。それでもなお、ゲーセンにこだわり続ける理由は一体なんなのだろうか。
「『eスポーツ』全盛で、オンラインが当たり前になっているなか、オンラインでは味わえないものがあることがゲーセンの良さ。言葉にするのは難しいんですけど、対面で戦うと、いろいろなものが伝わるんですよ、生のライブ感というか。そして勝った負けたで、一喜一憂するのがいい」
「ゲームを通しての相手の会話」によって、昨日までは敵だったライバルが味方となり、チームで戦うという漫画のような展開も実在する。
「ここには、中学生から50代後半くらいまでいろんな人が来る。警察官もいれば消防士、フリーター…普通に生活していたら出会えないような人と、1つのゲームが好きだという共通の話題だけで知り合え、仲良くなれる。学歴とか社会的な地位とか一切関係なく、ゲーム強ければちやほやもされる。そういうことが生まれる場所なんです。
数は少ないですが、ゲーセン世代のお父さんに連れられて来る子どもたちや、自分で調べておもしろそうと思って来る高校生とか、そういうゲーセンの良さを知らない人には教えてあげたいし、知り尽くしている人には、残してあげたい。『行けば誰かいるじゃん』って気軽に行ける場所って、すごい大事だと思うんですよね。ここを残すことは僕の使命で、どんなに赤字になってもつぶすことはあり得ません。僕にとってゲーセンは“人生”。何があってもこの店をずっと守っていく覚悟を持っています」
取材・文/衣輪晋一
(提供:オリコン) |
 |
| ユニバーサルグラビティー代表・松田泰明氏 (C)oricon ME inc. |
【関連記事】 |
| 【写真】今や貴重な“ブラウン管筐体”も並ぶ…『ゲームニュートン』大山店店内の様子 |
| 【漫画】「昭和男子×ファミコンあるある」にほっこり…懐かしい'昭和アイテム'も続々登場 |
| 【写真】時価50万円!金色の『バイナリィランド』ほか高額レアファミコンソフト全20タイトル |
| 【写真】オーナー・北島三郎もにっこり!美少女化したキタサンブラック |
| 【動画あり】ミニスカ衣装で美脚チラリ!話題のうまぴょい!ポーズするウマ娘声優たち |